わたし自身は割と大雑把な人間です。あなたはどうですか?
【大雑把】という言葉は【几帳面】の対義語として、性格を表すときによく使いますよね。
どちらかというと、
「雑」とか「がさつ」とか、
マイナスなイメージのほうが大きいかもしれません。
しかし、大雑把の使い方をちょっと変えて
「もっと耳障りのよい言い回し」にすると
大雑把はとてもポジティブなイメージに変わるのです。
大雑把な性格をポジティブに言い換える
代表例として挙げられるのが
「おおらか」や「小さなことにこだわらない」などでしょうか。
ちょっと難しい言葉だと「鷹揚(おうよう)」もありますね。
バレエの名作「眠れる森の美女」の1幕で、オーロラ姫の誕生を祝っていろんな妖精たちがやってきて贈り物をするのですが、
そのなかに優雅さを授ける「鷹揚の精」という妖精がいます。
鷹揚の精の踊りは、発表会でもおなじみのヴァリエーションなのですが、羽ばたく翼のような優雅な手の動きが特徴的な踊りです。
【大雑把】が一歩間違えれば
優雅さをも意味する【鷹揚】に変わるのですから、
言葉の言い換えによって、恐ろしいほどイメージ操作ができるのです。
短所のようにみえる性格が「長所」に
欠点やデメリットが「魅力やメリット」に変わってしまうわけです。
ここからは、【大雑把】の言い換え例として
大雑把な性格を魅力的に言い換えるポジティブ例文
大雑把をビジネスや論文で使う場合の堅い表現の例
についてまとめていきます。
大雑把の言い換え【短所は長所の裏返し】面接や履歴書で使える表現

就職活動の面接や履歴書に、自分の長所や短所を書く際に、
よく読んでみたら長所も短所もおんなじような事を書いているって気づくことありませんか?
短所と思っていることが、ある場面では長所に変わり、
逆に長所と思っていることがある場面では短所に変わる。
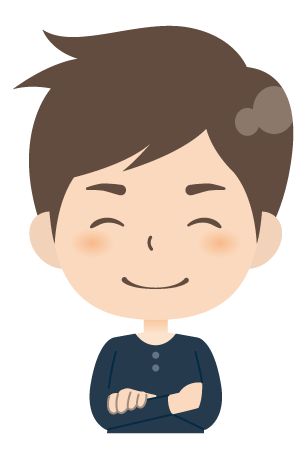
結局は同じ人格があらわれているだけじゃん
という事に気づくと、
【短所は長所の裏返し】という言葉の意味がストンと腑に落ちます。
せっかくなので【大雑把】を例にしてみましょう。
「私の長所は、決断力が速く、すぐに行動できることです。
小さなことをうだうだと考えているよりも、とにかくやってみよう!と、なんにでもすぐにチャレンジできてしまいます。
こだわりすぎて作業が遅れる、ということがないので、スピード感をもって仕事することができます。
短所は、そそっかしいところがあり、ちょっとしたケアレスミスが多いことです。
細かい部分を詰めずに先に進めてしまったために、やり直しになってしまうことが過去にあったので、日頃から注意しています。
また、細かい部分になると仕事が雑になってしまう部分があるので、ひとつひとつ丁寧に確認をとって進めるように気を付けています。」
どうでしょうか。
長所の部分も、短所の部分も
実は「大雑把」な性格のことを話していると思いませんか?
【大雑把】の一番の強みは、瞬時に物事のおおまかな概要を把握して行動にうつせる点です。
企画職やディレクター、営業・接客業など
全体を把握するポジションには非常に向いている性格ですよね。
決断がはやくて行動力のある人は、チームリーダーなどにうってつけです。
全体像を把握しながら前向きにチームをひっぱっていけます。
逆に【大雑把】の弱点は、
面倒な仕事が雑になりがちな部分や
アバウトすぎてどんぶり勘定になってしまう部分です。
きっちりと数字を合わせないといけない
経理や総務の仕事などには、不向きな性格と言えますね。
【短気・頑固・せっかち】短所の言い換えポジティブ9選!も合わせてどうぞ

大雑把の言い換え【ビジネス・論文編】熟語や言い回しの例文

次に、性格を言い表す場合ではなく、
物事の様子をあらわす【大雑把】について
詳しくみていきましょう。
大雑把は、『大きく雑に把(にぎ)る』と書くことから、
大まかに把握する、という意味で使われます。
ビジネスの場面などでは
「とりあえず大雑把に理解していただけたら大丈夫です。」
などと使ったりします。
以下、「大雑把」をビジネスや論文など堅い場で使用する際の
類語や言い回しなどを例文とともご紹介していきたいと思います。
【例文】大雑把の言い換え・類語
「今回の商品開発の方向性を簡単にまとめてみました。
まだ粗削りですが、ここから詳細を詰めていければと考えています。」
→ざっくりとした、まだ洗練されていない、という意味で、まさに大雑把の類語ですね。
「クライアントに説明するときに、伝わりやすいようにラフ画を描いてもらえると助かる。」
→クリエイティブ業界では頻繁に使われる「ラフ画」は、
ラフに=大雑把に という意味からきている造語です。
ラフ画、というくらいですから本当に殴り書きのような絵の場合も多いです。
「まずは、先日起こった事件の概要を説明します。」
→物事の大まかな趣旨や流れを指す「概要」はまさに「大雑把な内容」ということです。
「読者にわかりやすいように、最初に作品のあらましを述べる。」
→「概要」とほとんど同義語なのが「あらまし」で、文学作品などの場合によく使われます。
「杜撰(ずさん)な施工管理に非難の声が上がっている。」
→ニュースなどでよく耳にする非常にネガティブなイメージの言葉ですが、大雑把の雑のイメージを切り取ったような類語です。
まとめ

いかがだったでしょうか。
余談ではありますが、私の住む地方では、大雑把やだいたい、という意味の方言のひとつに「てげてげ」という言葉があるんです。
県民性もあるのかもしれませんが、これが不思議なことにものすごくポジティブに使われているのです。
「てげてげ」には、他にも「力が抜けた」とか「がんばらない」という意味も含まれており、
「てげてげにやる人」とはネガティブなイメージよりもむしろ
「頑張りすぎず、上手に手を抜いてできる人」という、すごく要領のよい人のイメージが強いのです。面白いですよね。
ここまで読んできて、あなたのなかの「大雑把」という言葉のイメージがだいぶ豊かになったのではないでしょうか。
まさに「大雑把」ですが、言葉の意味ってほんとうに「ざっくりと」したイメージで捉えておくと
さまざまな場面でぱっと使えたりしますので、ぜひ普段から試してみてくださいね。
